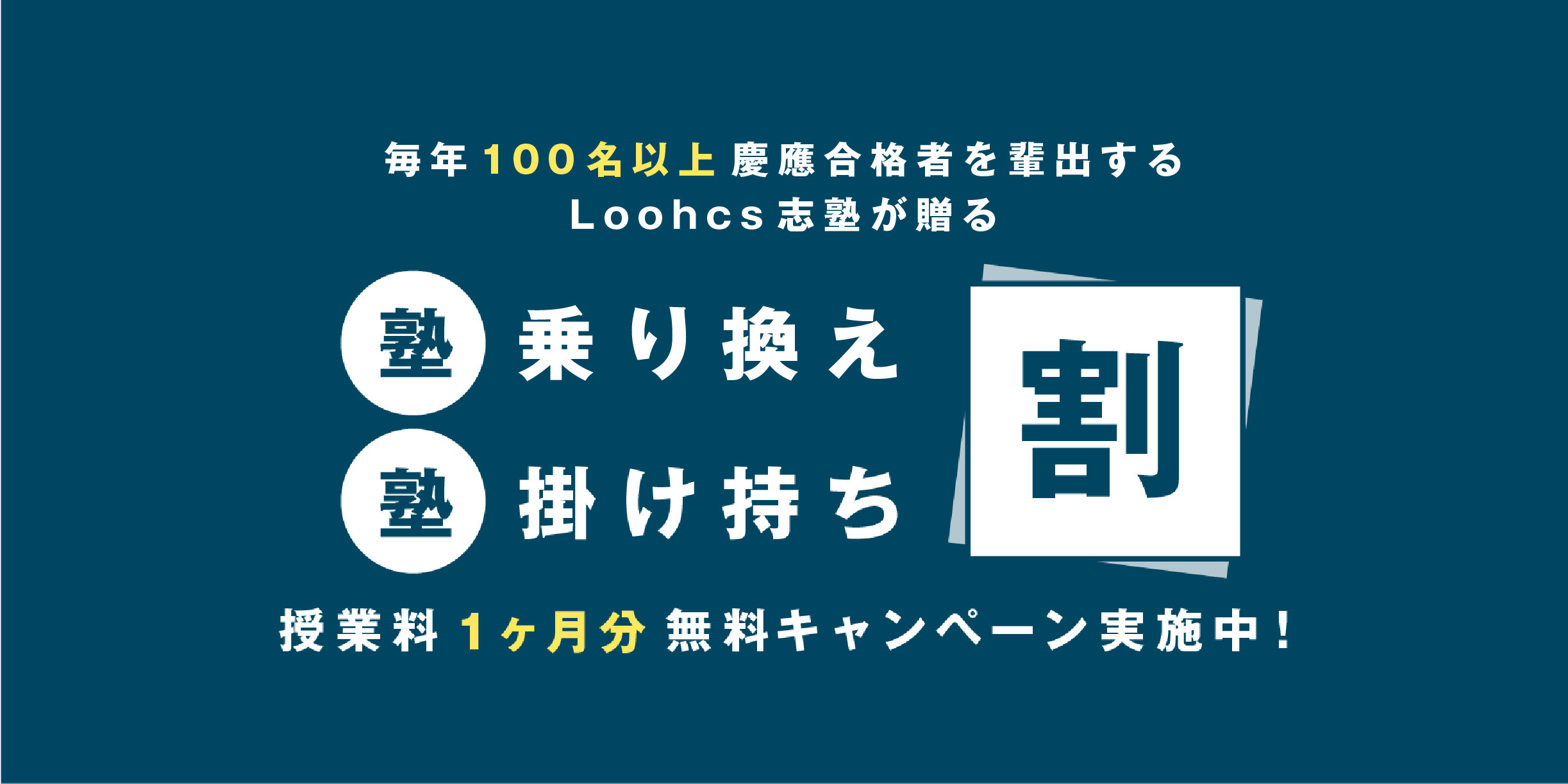アドミッションポリシーとは?言葉の意味や分析方法・志望理由書への反映方法まで解説

こんにちは、ルークス志塾柏校で校舎長を勤めている大城です!
今回は総合型選抜(AO入試)で重要な「アドミッションポリシー」について解説します。
アドミッションポリシーと聞いても、
- 「総合型選抜で重要って言われるけど、アドミッションポリシーって何?」
- 「志望理由書や出願書類に書いた方がいいの?」
- 「志望理由書や出願書類に書くなら、書き方はどうしたらいい?」
と、まだまだわからないと思っている方が多いのではないでしょうか。
そこで!今回は、たくさんの受験生を指導してきた僕が、「合格するためのアドミッションポリシーの分析方法」と題して、その意味や志望理由書・出願書類への書き方などを紹介します!
ぜひ参考にしてみてください!
総合型選抜(AO入試)で重要な「アドミッションポリシー」とは何か?言葉の意味を解説します

アドミッションポリシーとは、「大学の受け入れ方針」のこと
アドミッションポリシーとは大学の入学者受け入れ方針です。
この中に”求められる学生像” ”卒業後の人物像” ”どういう人材を育てたいのか” ということが明記されています。
合格するためには、なぜアドミッションポリシーを知る必要があるの?
それは、アドミッションポリシーを知らなければ、どんなに綺麗な文章の志望理由書でも、内容のいい志望理由書でも、合格することができないためです。
総合型選抜入試の前身、AO入試のAはアドミッションのAからも来ていることからわかるように、アドミッションポリシーと受験生のマッチングは非常に重視されています。
例えば、大学側が「英語ができる生徒が欲しい」と言っているのに、「スポーツなら誰にも負けません!」と伝えてしまうと、どんなにすごい実績でも合格することは難しいでしょう。
上記の例はわかりやすく説明しましたが、もう少し具体的にお話します。
こちらは、2022年度明治学院大学自己AO入学試験の法学部消費情報法学科の出願資格を一部抜粋したものですが、そこには
受験生は、消費情報学科の内容・特徴をよく理解した上で自分がどのような能力・経験が本学科のどの部分に適しているかアピールしてください。
2022年度明治学院大学自己AO入学試験 ページより
とあります。
この経験や能力がどいういう部分にあっているアピールせず、自分が大学でやりたいことだけを書いてしまうと、どんなにいい内容でも合格することはできません。
アドミッションポリシーを対策に活かそう
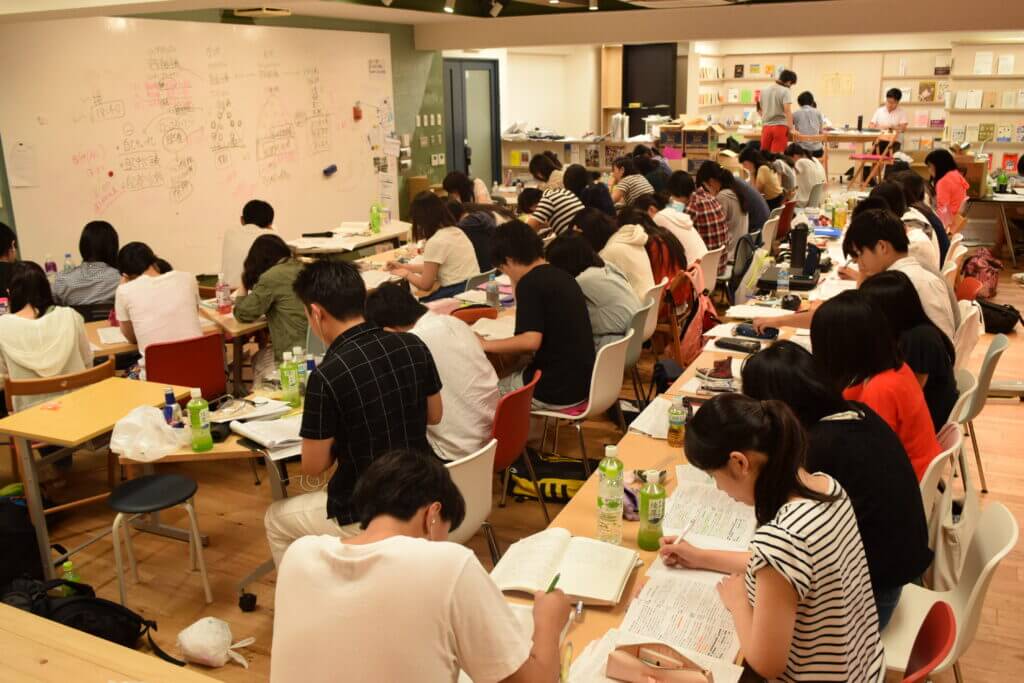
アドミッションポリシーを知ることの重要性はわかったと思いますが、それをどのように合格に繋げていけるかイメージがつかないという人もいるのではないでしょうか?ずばり、アドミッションポリシーについて重要な点は6つあります。
- ①:アドミッションポリシーをいつ・どこでチェックすべきか
- ②:志望校選びの参考にしよう
- ③:アドミッションポリシーを分析しよう
- ④:アドミッションポリシーと比較して足りない部分を補おう
- ⑤:出願書類に反映させよう
- ⑥:面接で答えられるようにしよう
それでは、アドミッションポリシーを知るところから合格まで順を追って説明していきます。
ポイント①:アドミッションポリシーをいつ・どこでチェックすべきか
時期としては、遅くも高校3年生になる前には確認しておくとよいでしょう。
興味のある大学のアドミッションポリシーを見てみることで、そこが本当に自分の思っていたような学校なのかを見極めることができます。
アドミッションポリシーは、大学ホームページ、パンフレットなどで確認することが出来ます。
大学で1つのポリシーを設けていることもありますが、多くの場合は学部ごとにも明記されているので、各学部についてもチェックしましょう。
ポイント②:志望校選びの参考にしよう
先ほども少し書いた様に、アドミッションポリシーを読むことで、大学のカラーや実際に学べることへの理解が深まります。
自分に合っている学校かどうか、学びたいことが本当に学べるのかなどを良く調べて、志望校を決めていきましょう。
ポイント③:アドミッションポリシーを分析しよう
アドミッションポリシーは、出願する志望校全てにおいて対策しなければなりません。内容は、それぞれの大学によって異なります。
それぞれについて理解しなければ、総合型選抜入試を攻略することはできないので、丁寧な分析が求められます。分析方法については、後ほど詳しく解説します。
ポイント④:アドミッションポリシーと比較して足りない部分を補おう
大学が求める学生像と、自分自身を比較してみて、足りていない部分を対策し強化していきましょう。
例えば、情報系のスキルを求められている場合は情報系の資格試験に挑戦してみたり、文化横断的な人材を求められている場合は国際交流の経験ができる活動に参加してみたりするとよいでしょう。
ポイント⑤:出願書類に反映させよう
大学に対して、一番初めに自分自身をアピールするチャンスが出願書類です。
ここでマッチングが見極められることになるので、出願書類には明確に反映させる必要があります。
反映させるとはどういうことなのか、については後ほど詳しく説明します。
ポイント⑥:面接で答えられるようにしよう
面接でも大学と受験生の素質とのマッチングが重要視されます。
出願書類の内容を自分の言葉で説明できるようにしておくのはもちろん、アドミッションポリシーについての直接的な質問にも答えられるようにしておきましょう。具体的には、アドミッションポリシーを読んだか、どの点に共感し、入学後どのように実践していきたいかなどを質問されることがあります。
合格するためのアドミッションポリシー分析方法

合格する志望理由書を書くためには、志望理由書を書く前にアドミッションポリシーを分析する、ということが重要です。
学校の先生も「アドミッションポリシーは理解しなさい!」と言うと思うのですが、具体的にどうやって分析したらいいかということをあまり教えてくれないのではないでしょうか。
そこで、具体例を出しながら、アドミッションポリシーの分析方法を3つ紹介します!
- 分析法①:大学の教育方針・教育理念を読み解こう
- 分析法②:学長の言葉を読み解こう
- 分析法③:3つのポリシーを読み解こう
それでは、順を追って解説していきます。
分析法①大学の教育方針・教育理念を読み解こう
まず見るべきポイントは、「大学の教育方針・教育理念」を読み解くことです。
大学は教育機関であるため「こういう生徒を育てたい」という方針があり、それに基づき「こういう生徒を育てたいから、こういう人材に入学してほしい」という形でアドミッションポリシーを決めていきます。
ですので、まずは大学の大元の教育方針・教育理念を知りましょう。
例えば、慶應義塾大学のSFCでは
多様で複雑な社会に対してテクノロジー、サイエンス、デザイン、ポリシーを連関させながら問題解決をはかる。そのために設立されたのが慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)です。既存の学問分野を解体し、実践を通して21世紀の実学を作り上げることが私たちの目標です。
慶應義塾大学SFC公式HPより(一部抜粋)
と記載があります。ここから「複雑な社会問題を発見し、さまざまな学問領域を活用して解決できる人を育てたい」ということが読み解けます。
分析法②学長の言葉を読み解こう
次に見るべきところは、学長の言葉です。多くの大学では学長の言葉に「わかりやすく、こういう生徒を育てたい」というメッセージが含まれています。
例えば、慶應義塾大学SFCの総合政策学部の学長の言葉は以下のようになっています。
現実の世界に存在する問題は、いずれも領域横断的です。そうだとすれば、学際的な領域に踏み込む学問をつうじてこそ、政策を考える力を養うことができるのです。
私たちは、総合政策という学問をつうじて、未来を見通す展望力、状況を捉える分析力、政策を設計する構想力、政策の意義を訴える説得力、政策を実施する実行力とともに、それらの力を総合する力を備えた学生を育てるのです。
慶應義塾大学SFC公式HPより(一部抜粋)
ここからもわかるように、「社会の問題を解決するために、領域横断的に学び、分析して、政策を実行していく」生徒を育てたい、とされています。
分析法③3つのポリシーを読み解こう
大学には3つのポリシー
- ディプロマポリシー(卒業の認定に関する方針)
- カリキュラムポリシー(教育課程の編成及び実施に関する方針
- アドミッションポリシー(学者の受入れに関する方針)
を設定しています。こちらも読み解きましょう。
「え、アドミッションポリシーだけ見ればいいんじゃないですか?」
と思う方もいるかもしれませんが、ぜひ3つのポリシーを見てほしいです。
というのも、ディプロマポリシーは「卒業までにこういう力をつけてほしい」、カリキュラムポリシーは「その力をつけるために、こういう教育方針になっています」ということが書いてあります。
つまり、構造的には「卒業までにこういう力をつけさせる(ディプロマポリシー)、そのためにこういう教育方針となっている(カリキュラムポリシー)、だからこういう力をもった生徒に入学してほしい(アドミッションポリシー)」というように、ディプロマポリシーに合わせてアドミッションポリシーが設定されています。
ですので、3つのポリシーを読み解くことでやっとアドミッションポリシーが理解できるのです。
では、慶應義塾大学SFCの総合政策学部の3つのポリシーを見てみましょう。
ディプロマポリシー
「実践知」を理念とします。慶應義塾の伝統である「実学(サイヤンス)」を継承し、複雑な社会現象のなかから課題を発見し、その解決に向けた政策を立案することを可能にする態度・知識・技能を身につけた人材を育成します。
カリキュラムポリシー
学生が自ら能動的に問題を発見・分析・解決する能力をつけるために、研究会中心の教育課程を編成しています。総合政策学部では「政策デザイン」「社会イノベーション」「国際戦略」「経営・組織」「持続可能なガバナンス」の五つの研究領域をゆるやかに設定するとともに、それらの横断的・学際的な教育・研究を積極的に後押しします。
アドミッションポリシー
総合政策学部は「実践知」を理念とし、「問題発見・解決」を重視する学生を求めます。問題を発見・分析し、解決の処方箋を作り実行するプロセスを主体的に体験し、社会で現実問題の解決に活躍することを期待します。したがって、入学試験の重要な判定基準は、基礎学力に裏付けられた、自主的な思考力、発想力、構想力、実行力の有無です。
慶應義塾大学SFC公式HPより(一部抜粋)
となっています。つまり、
- ディプロマポリシー:社会問題を様々な角度から分析・発見し、政策を立案できる
- カリキュラムポリシー:そのために、能動的に問題発見・分析・解決能力を身に付けさせたい。
- アドミッションポリシー:だから、問題発見・解決を主体的に体験して活躍している人を求めています。
となります。
志望理由書にアドミッションポリシーを反映する書き方

分析したアドミッションポリシーを元に「自分はそういう生徒です!」と志望理由書に反映しアピールしていきます。
ここでよく聞かれるのが「アドミッションポリシーって志望理由書にそのまま書いた方がいいですか?」ということです。
結論を言うと、いい志望理由書にするには「アドミッションポリシーをコピペせず、さりげなくアピールできるよう」にしましょう。
やってしまいがちなのは、HPに書かれているアドミッションポリシーをそのまま書いてしまうことですが、これでは試験官に「ただコピペしただけじゃん」と思われてしまいます。
ですので、アドミッションポリシーは書き写すのではありません。
志望理由書において自分自身の志や経験を説明する中で、アドミッションポリシーに適った素質を持っていることを示していきましょう。
例えば、慶應SFCでは「分野横断的に」、「問題発見・解決能力」、「主体的な体験」が求められているため、それらを中心に志望理由書を書いていきます。
こちらのページで、合格者の志望理由書を実例で解説していますので、参考にしてみてください!
合格者書類から学ぶ!慶應SFCの総合型選抜(AO入試)志望理由書を書く5つのコツを解説します。
合格する志望理由書を書くためには、アドミッションポリシーの分析や添削が大切!

以上、アドミッションポリシーの分析法や志望理由書への書き方などを、合格者の実例で解説しました!
このようにアドミッションポリシー1つにとっても、ここまで分析が必要です。さらに、分析にはコツや経験も必要ですし、志望理由書にも理解した上で反映していかなければなりません。
意外と難しいな・・・。と思った方は、ぜひ一度無料相談会にお越しください!
大学の情報や合格者の志望理由書をお見せしながら、その大学が求める生徒像(アドミッションポリシー)のお話もします。
志望理由書の書き方に悩んでいる、アドミッションポリシーが読み解けない!と言う方は、ぜひ一度お越しください。総合型選抜(AO入試)の合格に向けて、解説させていただきます!