合格できる小論文を書けるようになる極意!~守破離の極意~
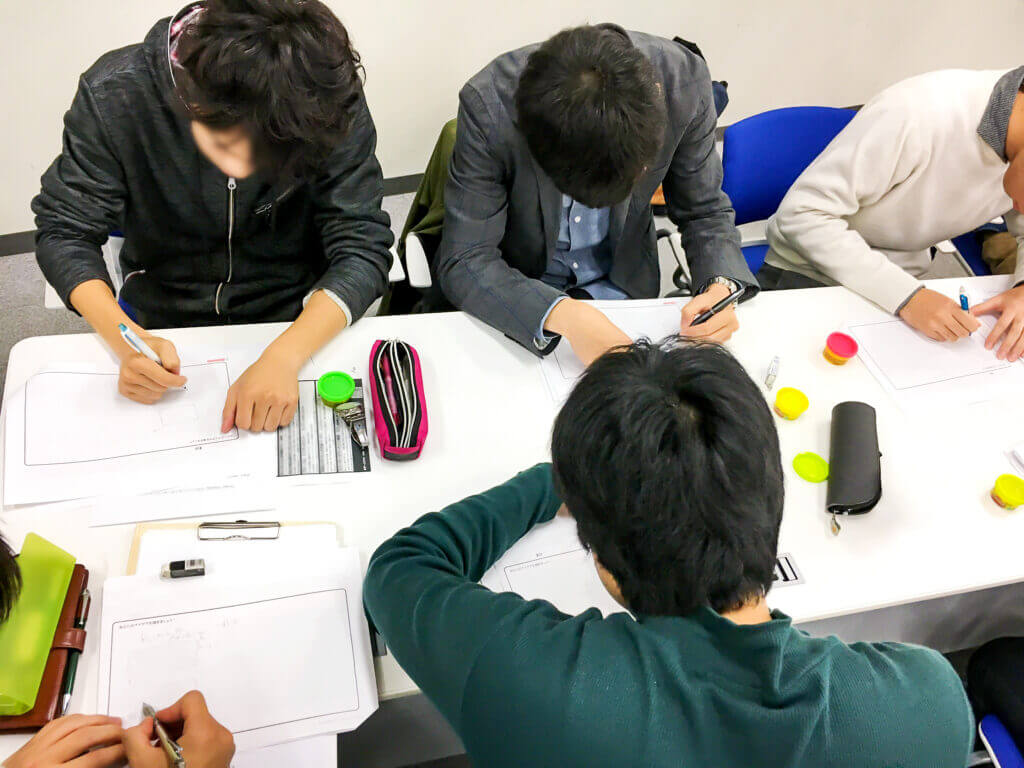
総合型選抜(AO入試)では、多くの場合小論文を書くことになります。小論文の試験では、文章として論理的な構造を取っていることと同時に個性的なものであることが求められます。
この両者のバランスをとることは非常に難しいですし、受験生も疑問に思う部分ではないでしょうか?
この記事では、正しい構造と個性の両方を併せ持った文章を書けるようになるための極意を紹介します。
試験官の印象に残る小論文の極意は、「守破離」である

文章としての構造を成り立たせつつ、個性的なものを書けるようになるには、「守破離」というプロセスをとる必要があります。
「守破離」とは、簡単に言えば、型を身に着けた上で、自分なりの形を作ることです。この小論文の極意といえる「守破離」について詳しくみていきましょう。
「守破離」とは
「守破離」とは、茶道などの日本の芸道で使われる言葉です。守破離のプロセスを通って一人前になることができると言われています。
「守」
まずは、型を学び、それを守って実践することが必要です。小論文で言えば、序論・本論・結論といった典型的な構造にあたります。型をしっかりと学び、それに則ったアウトプットをすることで、型を自分のものとして身に付けます。
「破」
次は、破という文字からわかるように、型を壊す段階です。型を使って書いていく中で、より良い形と言うのを模索していきます。工夫を続ける中で、結果として、型とは少し異なるけれど、自分の伝えたいことにおいては、最適な形が見つかる場合があります。
「離」
最後に、型を離れる段階になります。ここでの型を離れるとは、ただ単に型と異なる形をとるという意味ではなく、自分なりのやり方を確立するということです。
「破」の段階で型にとらわれずに色々なことを試す中で、自分の個性を活かすことのできる方法がわかってきます。小論文で言えば、他者と差別化できるような個性的な文章を書くことができるようになります。
小論文対策における守破離のプロセス

守:小論文の型を学ぼう
小論文には、読みやすく説得力のある構造が存在します。
ここでは5段階エッセイという型を紹介します。
1. 主張…自分の主張の決定
2. 理由…自分の主張の根拠
3. 具体例…字数や内容によっては書かなくていい場合も
4. 反駁…他者の視点+その根拠
5. 主張…必ず1と統一させる
「守」の段階としては、まずはこの5段階に則って自分の主張を書いてみましょう。意識せずともこの5段階を使えるようになるまで何度でもこの型に沿って練習するのがおすすめです。
破:自分の書きたいことにこだわって書いてみよう
「守」の段階では、基本的に型の全ての要素を毎回同じくらいの分量で書いていくことになると思います。
次は、自分が詳しいこと、特に訴えたいことがより魅力的に伝わるにはどうしたらよいか、というのを意識して書いてみましょう。特定の根拠がとても長く具体的になってしまって、逆に最後の結論があっさりしてしまう、といったことが起きてしまうかもしれませんが、それでもOKです。
型に拘り過ぎずに何度も書いてみることによって、そこまで崩すとバランスが悪くなってしまうのか、逆にどこまでだったら型を逸脱しても大丈夫なのかが自分の中でわかってきます。
離:自分らしい小論文を完成させよう
「破」の段階で、型と自分らしさを両立する加減がつかめたら、ついに「離」となります。
冒頭の書き出しをキャッチーな言葉にしてみたり、自分の訴えを存分に書いたりと、個性あふれる小論文を書いていきましょう。ここまでに「型」をしっかり身に着けていれば、自分らしくも論理的で読みやすい文章を自然と書けるようになっているはずです。
「離」の段階では、色々なお題の小論文に挑戦し、自分らしい小論文を書く力を確かにしてきましょう。どんな分野のお題でも個性を出せるように、社会問題についての知識なども同時に蓄えていくと良いです。
小論文の極意は時間をかけてものにしよう

受験生の中には個性を出さなければと考えて、いきなり「離」を目指してしまう人も多いのではないでしょうか?しかし、そうするとトリッキーではあるけれど、非常にわかりにくい文章が出来上がってしまいます。
「守破離」に則って、いきなり自分の個性を考えるのではなく、型をしっかりと身に着けることで、論理的で読みやすいけれど、個性的な小論文を書けるようになるのです。急がずに時間をかけて練習を積み重ねていきましょう。

